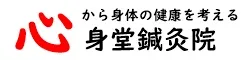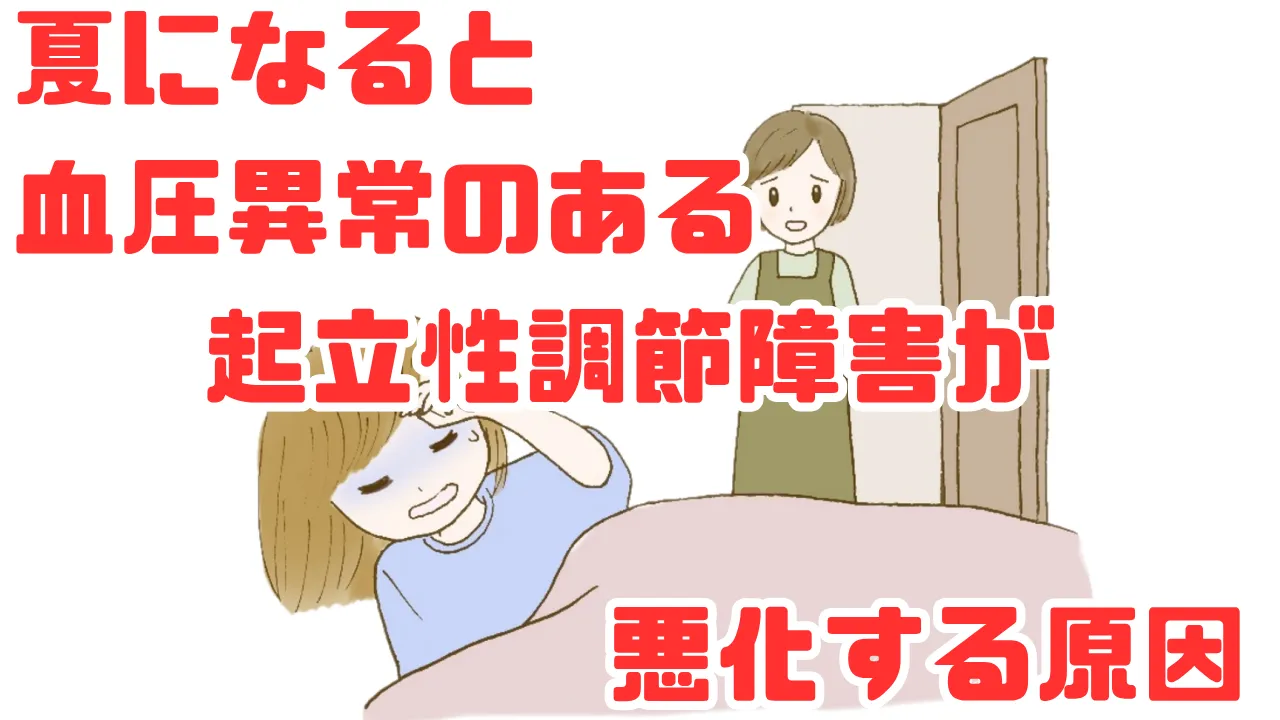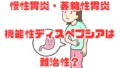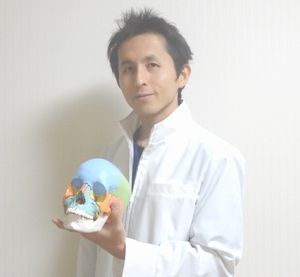
こんにちは、心身堂鍼灸院の佐野です。
お子さんが夏になると体調が悪化してしまうと、毎日とても心配ですよね。今回は夏になると血圧異常のある起立性調節障害のお子さんの体調が悪化する原因について一緒に考えていきたいと思います。
悪化する原因を理解することで、対処法も考えることができるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
結論:気温が上昇すると血圧が下がりやすくなるので、体調が悪化しやすくなる
起立性調節障害は血圧を適切に維持できないことで、朝起きられない、頭痛、腹痛、めまい、だるいなどの自律神経症状が生じる疾患です。
気温が上昇すると体温を逃がすために体は皮膚表面の血管を拡張させて放熱がしやすい状態を作り、更に発汗することで気化熱によって体温を下げようとします。
この体の調整機能が正常に働くことで、体温は調節される一方、血圧を適切に維持できなくなってしまいます。


血圧の維持が難しくなる2つの理由
血圧の維持が難しくなる原因は放熱効率を上げるための、皮膚表面の血管拡張と発汗が主な原因です。
皮膚表面の血管拡張がもたらす血圧低下
私達の体にある血液は、すべての臓器に同時に十分な血液を供給できるようにはなっていません。
自律神経が時間帯や状況に応じて、血液をどこに集中させるのかを判断し命令することで全身の細胞に栄養と酸素を行き渡らせ、老廃物の回収を行っています。
起立性調節障害のお子さんの場合、自律神経の機能低下だけでなく身長が急激に伸びたなど、身長の伸びに心臓の成長が追い付いていない場合に血圧が維持できなくなるケースもあります。
必要な血液を循環させる力の不足や血液量の不足が元々あるのが起立性調節障害のお子さんの体です。
その為、体温を下げる為に皮膚表面の血管を拡張させるとその分血管の容積が増えるため、必要とする血液量も増加します。
結果的に元々循環血液量が不十分な状態のところに、暑さに対する適応としてさらに追加で循環血液量が必要になるように自律神経が命令を出してしまうため、更に血圧の維持が難しくなって体調が悪くなりやすくなります。
皮膚表面への血液供給のために、胃腸への血流を減らすという反応も起こりやすくなるため、消化器系の症状が出やすいお子さんの場合は、食欲不振や腹痛、便秘や下痢といった症状も出やすくなります。
発汗により血液量が減少する
汗の原料は血液中の水です。血液は単純には「血球+水」でできていますので、汗で血液中の水が排出されると、血液中の水が減ることになります。
その結果、血液量が減少することになります。
起立性調節障害の治療で水分を多くとるよう指導されますが、血圧を維持するためにはそれなりの水が必要にもかかわらず、発汗によって水が体から減少してしまい、より血圧の維持が難しくなるのです。
短期的な対処と長期的な改善策
ここでは短期的な対処法と長期的な改善策について解説しますが、短期的な対処法をやりすぎると、長期的には悪化する方向に作用してしまうことがありますので、バランスを取りながら実行することが大切です。
短期的な対処法
短期的には気温の上昇により体が温まってしまうことで、体温を下げようとして、血管の拡張や発汗が促進されて血圧が下がって症状が悪化することを説明しました。
単純な対策にはなりますが、外気温を低めに調節して体温を下げることで、自律神経の反応が起こらないように先回りして対策することが一つの対処法になります。
エアコンが少々強めの部屋で過ごすようにする、プールなど水圧をかけながら水で冷やすと、血管拡張や発汗が抑えられるので短期的な対処法として有効です。
一つ注意点があって、体温を下げる目的で、アイスやかき氷、冷たい飲み物などで体を冷やそうとするのは避ける必要があります。
胃腸は冷えに弱く、食べ物で冷やされると血管が収縮してしまい腹痛や食欲不振など消化器系の症状も出てきやすくなってしまいます。
血圧が下がって頭痛やめまいがひどい場合には、涼しい部屋で横になっておくのが最も効果的ですが、涼しい部屋でも体を動かすことは継続することが大切です。
長期的な改善策
基本的な生活習慣を整えるなどはもちろんですが、起立性調節障害の改善には下半身をよく使った運動を季節に関係なく、継続的に行うことが大切です。
起立性調節障害になるとだるさから運動を嫌がるようになったり、気力の低下から寝転がってスマホやゲームをずっとしているなど、運動不足が加速します。
血圧を維持できるようになるには、足に血液が溜まらないようにすることと運動によって心臓と肺の機能を高めることが重要です。
体を起こすとすぐに頭痛が出てきてしまうほどの重度の場合でも、寝た姿勢でのエアロバイクによる運動をすることで改善が見られたという報告もあります。
体調不良がなるべく最小になるような姿勢で下半身をよく動かす運動を長期間継続することが大切になります。
体が凝り固まって血液がどこか一部(例えば背中など)に停滞してしまって、それが原因で利用できる血液量が不足して血圧を維持できなくなっている場合には、鍼灸で停滞してしまっている血液を流してあげることも有効です。
注意点
ごくまれにではありますが、起立性調節障害と診断されているにも関わらず、心疾患が見落とされている場合があります。
その場合には運動するなど心臓に負担がかかると、心拍数が急上昇して苦しさを訴える場合があります。
一般的な心電図検査では正常と診断されていても、運動時にしか不整脈がでない心疾患もあるため、運動に連動して心拍数の異常な上昇がみられる場合にはホルター心電図での検査が必要になります。
まとめ
夏の暑さは体温調節のために血管を拡張させ、発汗を促します。
起立性調節障害のお子さんにとってはこれが血圧の低下を引き起こし、体調をさらに不安定にしてしまう原因になる場合があります。
暑さによる影響を最小限に抑えるためには、室温の調整や水分補給、適切な運動など、日常生活でできる工夫がとても大切です。
また、体調に合わせて無理のない範囲で継続的に下半身を動かすことで、血流や自律神経のバランスが整いやすくなります。
お子さんの体調不良に対してできることを一つずつ積み重ねていくことで、少しずつでも前向きな変化が期待できます。
当院での改善をご希望の方は起立性調節障害をご覧ください。
遠方で通院が難しいが、起立性調節障害について相談されたい方はオンラインカウンセリングをご利用ください。