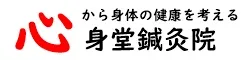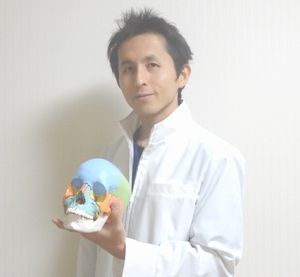
こんにちは、心身堂鍼灸院の佐野です。
暑い日が続くと外に出るのもためらってしまいますよね。でも、ずっと家にいるわけにもいかず、どうにかして熱中症を防ぎたいところです。
今回は熱中症のメカニズムを理解して、熱中症になりにくくする方法について考えていきたいと思います。
結論:熱中症になりにくくするには暑熱順化(体を暑さに慣れさせること)が鍵となる。
本題に入る前に、まずは、熱中症についての理解を深めていきましょう。
熱中症は体温の調節機能がうまく働かなくなり、熱が体にこもってしまった結果体温が異常に高くなって発症する障害の総称です。
熱中症の発症パターンには大きく以下の二つのパターンがあります。
塩分・水分不足パターン
体温を下げるためには発汗して気化熱(蒸発する時に熱を奪う現象)で体温を下げる方法が効果的です。
しかし、発汗によって体温を下げると、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)が体の外に出ていってしまいます。
その結果、体内の水分バランスが崩れて脱水状態となり、適切な発汗が制御できなくなり、その結果体温を下げられなくなってしまいます。
このパターンの予防法は脱水を予防することが有効なため、塩分(ミネラル)と水分補給が有効です。
塩分がなぜ必要なのか?というと、私たちの体は水を体内に留めておくのに塩分を必要とするからです。
水だけを飲んでいても、塩分が不足すると水を体の中にとどめておくことができません。
水だけを飲み続けることで逆に脱水になりやすくもなりますので、注意してください。
体温急上昇パターン
短時間に体温が上がり過ぎた場合も熱中症になります。
通常は前述した発汗による体温調節機能が先に働いてしばらくの間は体温の上昇を抑えるのですが、体温調節機能が対応するよりも早い速度で体温が急激に上昇してしまった時には水分補給をしていても熱中症になります。
夏場の車内などがこのような環境を作り出す代表的な場所です。
熱中症予防には塩分・水分補給を十分行うことが重要ではありますが、発汗システムが体温を下げるよりも早く体温が上がっていってしまうと塩分と水分補給をいくらしていても、熱中症になってしまいます。
対応は急激な体温上昇の原因となっている暑熱環境から、すぐに離れる。体を冷却することが有効です。
塩分・水分を補給していたら絶対に熱中症にはならないわけではないので、体温が上がり過ぎた状態にも気をつけましょう。
熱中症になりにくい体とは?
熱中症になりにくくする体の機能は次のような関係になっていることが重要です。
体の中で発生した熱+体の外から受け取る熱 ≦ 体温を下げる力
簡単に言えば、体温を上げる力よりも、体温を下げる(冷やす)力の方が強い状態を維持できれば基本的に熱中症にはならないことになります。
私たちの体は体温調節機能により、35.5℃〜37.5℃の間に収まるように調節されていますが、例えば運動時など筋肉を使用することで体の中で発生した熱が増えて体温は上昇します。
放熱や発汗などの冷却システムで、上昇した体温がコントロールできていれば、運動していても熱中症にはなりません。
熱中症になりにくくする為には、放熱・発汗によって体温を下げる力を高めて放熱や発汗による気化熱の作用で効率よく体を冷やすことができる体ということになります。
暑さに体を慣れさせることで体温調節機能を高めることを暑熱順化(しょねつじゅんか)といいます。
暑熱順化が起こった状態であれば、熱中症になりにくい状態になります。
暑熱順化を起こすには暑くなる前の対応が重要
では、暑熱順化を引き起こすために、夏の暑い時期に我慢して暑い中にいるのが良いのか?というと原理的にはそうですが、注意が必要です。
放熱・発汗によって体温を下げる力が弱い状態で、暑い場所にいると体温が急上昇して簡単に熱中症になってしまいます。
熱中症が起こりにくい体を作るためには、暑くなってからでは遅く、暑くない季節から運動やサウナなどによって体温をわざと上げて、放熱・発汗機能で体温を下げる訓練を行なっておくことが効果的です。
特に発汗を行う汗腺は使われることで発汗機能が向上して、体温を下げやすくなることが知られています。
もともと年中運動していて汗をかく習慣がある方であれば、暑い時期に暑いところにいることで、さらに暑さへ耐えられる体に変化していく可能性はあります。
だからと言って、無限に暑さに耐えられる体にはならないので、適度に体を冷やすことは大切です。
熱中症に強い体は夏以外の季節の過ごし方で決まる
日頃から運動して汗をかく習慣がない方が、熱中症になりにくくするには、秋、冬、春に運動やサウナなどで汗をかくことで発汗機能を高めていくことが有効です。
しかし、暑くなってしまうと体温調節機能も高くなっていないのに体温を上げて発汗を促そうとすると、単純に熱中症リスクを高めるだけなのでお勧めできません。
暑くなってしまってからの暑熱順化はリスクの方が高くなってしまうので、すでに暑くなっている時期は暑さをなるべく避けてエアコンの効いた涼しい部屋からでないで過ごすことのほうが賢明です。
涼しくなってきてから来年の夏前までの期間で、運動習慣を持ってよく汗をかくということを年間を通じて行なっていくと、来年以降、熱中症になりにくい体へと変化していくことが期待できます。
使わない発汗機能は失われていく
体の機能の多くは使われないとどんどん機能が低下していくようにできています。
これは使わない機能を維持するためにも体はコストをかけていることになるため、使わない機能をすぐにコストカットすることで資源を有効利用するために備わったために起こる現象です。
寝たきりで生活すると筋肉が衰えていくなどが分かり良い例ですが、汗腺の機能も同じように使われないことでどんどん機能低下がしていきます。
涼しい季節も運動せずに、汗をかかない生活を継続していくと暑さへの抵抗性はどんどん低下していきます。
つまり、熱中症になりやすい体へと年々変化していってしまうのです。
加齢でも汗腺の機能は低下する
加齢による影響で汗腺の機能低下、汗腺の数自体が減少していくことが知られています。
高齢になってくるといくら普段から発汗して、鍛えていてもある程度の機能低下は仕方がないと言える側面があるのは事実です。
しかし、使わないよりは使う方が機能が維持されますので、高齢者であっても涼しい季節は運動を継続して汗をかくことは大切です。
注意点として、暑さを感じる能力も低下しやすくなるため、気が付かずに熱中症になってしまうことがあります。
もともと加齢に伴って体内の水分量が少なくなるので、ちょっと汗をかいただけで脱水傾向になってしまいます。
塩分・水分補給をしっかりしながら運動をしていきましょう。
肥満気味の方は痩せましょう
極寒の地のアザラシなどを見ると分かりますが、寒い地域に生息する動物は皮下脂肪が厚くずんぐりむっくりした体型です。
つまり、皮下脂肪は保温能力が高く、放熱を邪魔する機能があります。
肥満体型の方が真冬の寒い時期でも暑がっている姿を見たことがある方もいらっしゃるかと思いますが、皮下脂肪が多いと体内の熱の放熱が邪魔されて、熱を保温して蓄積してしまいます。
BMIが適正になるように、体重管理も適切に行なっていきましょう。
筋肉量を増やすのも効果的
痩せている方が皮下脂肪による保温力がない分放熱能力が高いというメリットがありますが、筋肉が少ない場合には注意が必要です。
筋肉には多くの水分が含まれているため、痩せていて筋肉がないと発汗による水分不足がすぐにやってきてしまうことになります。
筋肉量をある程度増やすことで、体に保っておける水分量が増えるため、熱中症対策としては有効になります。
汗腺の働きを高めるには有酸素運動が有効ですが、筋肉量が多い方が水分不足からの熱中症を予防しやすくなるので、ある程度の筋トレもおすすめです。
暑さに対する抵抗性は遺伝の影響を考慮する必要がある
汗腺の活動は運動(特に有酸素運動)を継続することで、その機能が鍛えられることが知られています。
しかし、汗腺の数自体は胎生期に形成されるので、鍛えたからといって汗腺の数が生涯増えることはありません。
汗腺の数は遺伝的な影響が大きいとされています。
また、汗腺の機能も遺伝的な影響を受けることが報告されています。
そのため、普段から運動している・運動しないという条件を揃えたとしも、発汗機能がもともと高い人もいれば低い人もいます。
つまり、鍛えた方が熱中症にはなりにくいのは間違いありませんが、個人差が出ることになります。
部活動など、熱中症リスクが高い環境で運動する場合には、同じ条件でやっていても遺伝的に熱中症になりやすい子もいるため、塩分・水分補給はもちろんですが、体温が上がり過ぎていないかなど、こまめにチェックする必要があります。
夏の気温は上昇している
地球温暖化の影響もあり、明らかに夏の気温が上昇しています。
1920年ごろの最高気温は現在よりも2度ほど低く、最高気温が35度を超える猛暑日は0日でした。
人類は全身から発汗するという暑熱環境でも効果的に体温を下げるという特殊能力を獲得した比較的暑さに強い生物です。
だからといって、現在の暑さにまで完全に適応できる能力を持っていないとも指摘されており、それが熱中症を引き起こしやすくしている原因とも考えられます。
運動により鍛えることは重要ですが、遺伝的な限界もありますので、周りの人達が大丈夫だからと言って、あなたもその暑さに耐えられるとは限りません。
過信し過ぎず、体の変化を感じ取りながら、適切な対処が重要です。
<参考>
気温について|気象庁
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq3.html
過去の気象データ検索|気象庁
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
まとめ
熱中症には大きく塩分・水分不足による発汗機能の破綻から体温が下げられなくなる熱中症と急激な体温上昇で体温を下げる機能が追いつかなくなって異常な高体温になってしまう2つの熱中症があります。
暑さに対して「暑熱順化(しょねつじゅんか)」といって、汗をかく力や体温をうまく下げる力を機能を強化していくことで、熱中症になりにくい体に変わっていきます。
夏以外の季節に有酸素運動、サウナなどで汗をかくことを、継続していくことが熱中症になりにくい体づくりに役立ちます。
エアコンやこまめな水分補給は熱中症予防には効果的ですが、原理的には暑さに対する抵抗性を下げてしまうので、熱中症になりやすい体を作ってしまう側面があります。
日頃から運動習慣をつけておくことがなによりも、熱中症予防には有効と言えるかもしれません。