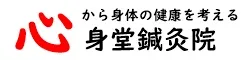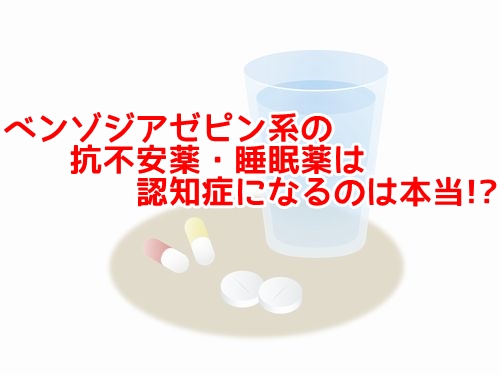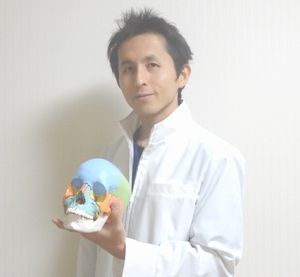
こんにちは、浜松市はりを刺さない鍼灸師の佐野です。
抗不安薬や睡眠薬に用いられるベンゾジアゼピン系の薬には、認知症リスクが高まるのではないか?という情報を目にして、やめたいという方も多いお薬です。
今回はそんなベンゾジアゼピン系のお薬をについて一緒に考えていきたいと思います。ぜひ最後までご一読ください。
結論:認知症のリスクが示唆される報告はあるが証明されているわけではない。
2014年頃にベンゾジアゼピン系の投薬が認知症のリスクを高めるのではないか?という報告がされ、メディアでも紹介されました。
ベンゾジアゼピン系に分類されるお薬一覧
・エチゾラム(デパス)
・クロチアゼパム(リーゼ)
・フルタゾラム(コレミナール)
・ロラゼパム(ワイパックス)
・アルプラゾラム(コンスタン、ソラナックス)
・ブロマゼパム(レキソタン)
・メキサゾラム(メレックス)
・クロナゼパム(ランドセン、リボトリール)
・クロキサゾラム(セパゾン)
・ジアゼパム(セルシン、ホリゾン)
・クロラゼプ酸二カリウム(メンドン)
・メダゼパム(レスミット)
・オキサゾラム(セレナール)
・クロルジアゼポキシド(コントール、バランス)
・ロフラゼプ酸エチル(メイラックス)
当院へは不安障害(パニック障害)や自律神経失調症による不眠症状で悩まれている方が来院されているので、医師から既に不安を抑える目的や睡眠薬としてベンゾジアゼピン系のお薬を処方されている方も多く来院されます。
服薬をされている方の中には、処方されているベンゾジアゼピン系のお薬についてご自身で調べて認知症のリスクが高まるといった報告を目にして不安になって辞めたいといわれる方も多いです。
基本的にはお薬に関しては医師の指導通りに使用するというのが大原則です。
全ての薬に言えることですが、リスクとリターンが見合っているのか?をまずは考えることから始めてみましょう。
処方してくれている医師の専門は?
軽度の不安症状や不眠を自覚した時に、いつもかかっている(一般)内科の先生に相談して処方してもらっているという方の場合は、専門医への受診を検討してみましょう。
なぜなら、不安や不眠は内科医の専門領域ではありません。その為ベンゾジアゼピン系の薬に関する知識や臨床経験がどうしても少なく、その薬に関する論文などもあまり読まれていない可能性が高いです。
自律神経の症状に対する処方は心療内科や精神科の先生の指導の下で使用されることが一番安全です。
日本の医療システムは医師免許を持っていれば専門外の薬も処方が出来てしまい、心療内科や精神科が予約3ヶ月待ち状態などになると、内科の先生も苦しい状態で過ごさせるより、とりあえずの対症療法として処方してくれる場合も多くあります。
(経営的な問題として、他科の薬の処方箋料を売り上げに出来るという問題は別件としてあります。)
もし、現在(一般)内科で処方してもらっている場合には、心療内科や精神科へ紹介状を書いてもらい、専門医に指導してもらうように切り替えていくことがまずは大切です。
ベンゾジアゼピン系の薬は通常2週間程度しか使わない薬
ベンゾジアゼピン系のお薬は依存形成が発生しやすい薬である点、徐々に耐性が付いてきて効かなくなっていくという薬の性質上、元々連続して使用する場合は2週間程度しか使用しないことが前提のお薬です。
不安障害(パニック障害、全般性不安障害)などの不安改善に用いる場合には、最初にSSRIの服薬を開始して効果が出てくるまでの2週間をやり過ごすためのつなぎとして使用されます。
SSRI系のお薬が効いてきた段階で、(パニック発作が起きている最中など)ストレスがかかって不安が強くて仕方がない時にだけ頓服で使用するといった限定した使い方に切り替わっていきます。
ベンゾジアゼピン系のお薬の使い方としては
①SSRIが効くまでの2週間だけ使用する。
②強いストレスがかかってパニック発作が起こった際に限定して使用する。
という2パターンのみとなります。
しかし、合うSSRIを見つけるのに手間取ってしまったり、見つけられない。
内科などでとりあえず処方されていて、依存が形成され、耐性も持つようになってだんだん効かなくなってから専門医を受診して、SSRIによる治療を開始するなど、初期対応を間違えた際に問題になってくることが多いお薬です。
認知症は脳の様々な場所が萎縮することが原因となる病気
認知症の方の多くは脳な様々な場所の神経細胞が減少して、萎縮することで発症する病気だと考えられています。
ベンゾジアゼピン系のお薬を累積で多く投与した患者さんの認知症の発症リスクが高いことが報告されたことで、ベンゾジアゼピン系のお薬が認知症を引き起こす可能性について報告がなされています。
この研究で一つ気を付けなければいけないことは、健康な人にベンゾジアゼピン系のお薬を投与して認知症の発症リスクが高まるのかを調べた研究ではないということです。
脳の萎縮が起こる原因
脳の萎縮の原因は以下のようなものがあります。
・ストレス
・不安
・うつ状態
・睡眠不足(睡眠障害)
・運動不足
ここで注目したいのが、運動不足以外はベンゾジアゼピン系のお薬の適用症状であるという点です。
脳の掃除を邪魔するという研究
認知症の原因の一つに脳内にアミロイドβという脳が活動する過程で作られてしまう、タンパク質でできたゴミが蓄積しすぎることで、神経細胞が破壊されてしまうと考えられています。
通常、このタンパク質のゴミ(アミロイドβ)はグリンパティックシステムといわれる脳内の老廃物を排出する機能によって脳内から取り除かれています。
しかし、ベンゾジアゼピン系のお薬やアルコールなどの影響で、グリンパティックシステムが邪魔されてタンパク質のゴミが蓄積してしまうのではないか?と考えられているのです。
マウスの実験ではマイスリー(ゾルピデム)を投与したマウスでは、グリンパティックシステムを起動する為の神経伝達物質であるノルアドレナリンが抑制されることが確認されています。
しかし、人間の脳でも同じなのか、別のシステムの為あまり影響がないのかなど、確実に認知症になると証明できているわけではありません。
認知症とベンゾジアゼピン系の薬には関係性が低いとする研究
成人5,400人以上を対象にしたオランダの研究では、ベンゾジアゼピン系の薬の使用が認知症リスクの増加との間に関連性は認められなかったと報告されています。(参考文献)
しかし、ベンゾジアゼピン系の使用が脳MRI画像を調べると海馬、扁桃体、視床の体積の減少(萎縮)する所見が見られ、特に海馬(記憶の中枢)は加速度的に萎縮が進むことが報告されています。
認知症は脳全体の萎縮であるのに対して、ベンゾジアゼピン系の薬の脳への影響は海馬、扁桃体、視床の体積の減少(萎縮)に限定しているということです。
認知症は海馬の萎縮が顕著ですが、扁桃体、視床だけでなくより広範囲な脳の萎縮を伴う病気ですので、記憶力の低下、時間や場所の感覚が曖昧、日常生活での判断や作業の困難、言葉の使用に支障、気分の不安定化、夜間不眠や徘徊といったより広範囲な脳の機能障害による複雑な症状が出ます。
一方、ベンゾジアゼピン系の薬を使用したことで起こる海馬、扁桃体、視床の萎縮は認知症よりも限定された範囲の脳の機能の喪失を招くと考えられます。
つまり、海馬(新しいことを覚えたり、過去の出来事を思い出したりする)、扁桃体(感情をコントロールする)、視床(嗅覚以外の感覚情報を脳の他の部分に送ったり、意識や注意力を調整)の機能が損なわれるだけで、他の脳の部位は正常である為、認知症とは別の状態になると考えられます。
そういう意味では認知症のリスクが増加するわけではありませんが、脳の機能が損なわれるという点では、長期連用はお勧めできる薬ではないといえます。
依存状態にしないことが大切
正しい利用の範囲内であれば、依存が形成されるリスクは低いのですが、依存形成と耐性が出来上がってしまうと、どうしてもベンゾジアゼピン系のお薬の投与量が増えます。
ベンゾジアゼピン系のお薬の依存は心理的依存と身体的依存の二つが存在します。
心理的依存とはそれを飲めば不安や不眠などの症状から解放されるため、服薬していないと不安になるのではないか?など、実際に身体的依存が発生していない状態でも、心理的に依存してしまっている状態。
身体的依存はベンゾジアゼピン系のお薬が切れてくるタイミングで、離脱症状が出てきて、不安・動悸・緊張・不眠などの自律神経症状が出てきてしまい、その離脱症状が出てしまう為、薬をやめることが出来ないというものです。
本来の疾患と区別がつかない
ベンゾジアゼピン系のお薬は不安もしくは不眠に使用するお薬です。
離脱症状が本来の疾患である不安障害(パニック障害)、睡眠障害と同じような症状が出てきてしまう為、疾患としてそのような症状が出てきているのか、離脱症状としてそのような症状が出てきてしまっているのかを区別することが非常に困難になります。
元の不安障害や睡眠障害による症状なのか離脱症状なのかを正確に判断することが出来ないのです。
その為、依存形成がされない範囲内での使用に留めておくことが重要になります。
他の選択肢を併用していく
ベンゾジアゼピン系のお薬は元々根治療法としてのお薬ではありませんし、依存性も高い為、使用に関しては短期的(2~3週間以内)に使うことが推奨されています。
使用していた目的がパニック障害などの不安に対する目的であれば、SSRIが効いてくるまでの2~3週間までのつなぎとして使う。頓服薬として辛い時だけ使用する程度が本来の使われ方です。
不安感のない不眠に関しては非ベンゾジアゼピン系のお薬に切り替えていくことも大切ですが、薬を変えても根本改善にはならない為、認知行動療法と生活習慣の改善が基本になります。
SSRIが副作用が強くて使えない、非ベンゾジアゼピン系では全然眠れない場合には投薬での治療が難しくなってきます。(20~30%ぐらいがSSRIが効果がない方がいます。)
漢方薬を使ったり、鍼灸や整体で不安症状が改善したり、不眠が改善する場合であればそちらを併用していくことも良いです。
しかし、最終的にはベンゾジアゼピン系のお薬が必要になってしまった原因(生活習慣、運動習慣、思考の癖、暴露療法)などを改善していくことが根本的な問題の解決になっていくことを忘れてはいけません。
まとめ
・ベンゾジアゼピン系のお薬で認知症リスクが上がるという報告はある。
・心療内科・精神科といったベンゾジアゼピン系のお薬の臨床経験の多い専門医を受診しましょう。
・ベンゾジアゼピン系のお薬で認知症リスクは高まらないという研究報告はあるが、海馬・扁桃体・視床の萎縮は認められる。
・投薬の戦略を理解し、正しくお薬を使いましょう。
・鍼灸や整体によって症状改善がされるようであれば併用を検討しましょう。
・根本的な改善は生活習慣、運動習慣、思考の癖などを改善していくことが必要です。
当院での改善を希望される方は、不眠症(睡眠障害)、パニック障害、自律神経失調症をご覧ください。
遠方で当院への来院が難しいけれど、心身の問題について相談したい方はオンラインカウンセリングをご利用ください。