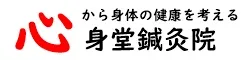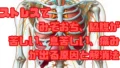結論:睡眠薬は大きく4種類があり、薬ごとにリスクが異なるので、医師とよく相談することが大切
睡眠薬を飲み始めるとやめられなくなるのではないか?と不安になる方も多いのですが、「睡眠薬」と一括りに考えてしまうと不安が強くなってしまいます。
依存性が高くやめるのが難しくなりやすい薬と依存性が低くやめることも比較的簡単な薬がありますので、とにかく薬なしでと考えるよりも、辛ければ一時的に薬を利用することも検討しましょう。
睡眠薬には大まかに以下の4種類に分けることができます。
ベンゾジアゼピン系
ハルシオン(トリアゾラム)、レンドルミン(ブロチゾラム)、サイレース(フルニトラゼパム)、ドラール(クアゼパム)etc..
非ベンゾジアゼピン系
アモバン(ゾピクロン)、マイスリー(ゾルピデム)、ルネスタ(エスゾピクロン)etc..
オレキシン拮抗薬
ベルソムラ(スボレキサント)、デエビゴ(レンボレキサント)、クービビック(ダリドレキサント)etc..
メラトニン受容体作動薬
ロゼレム(ラメルテオン)、メラトベル(メラトニン)etc..
それぞれ異なるメカニズムで睡眠を促しますが、睡眠薬を依存リスク順に並べると以下のようになります。
ベンゾジアゼピン系 > 非ベンゾジアゼピン系 > オレキシン拮抗薬 > メラトニン受容体作動薬
しかし、依存リスクが高いから効果が高いというわけではなく、状態に合わせてどの薬を使用するのか選択されます。
心療内科や精神科などの専門医であれば適切な薬を選んでもらうことが可能ですが、内科などの他科の医師が処方する場合は、必ずしもあなたに適した薬が処方されていないこともある為、睡眠薬を2週間以上継続使用するようであれば専門医に相談することが大切です。
それぞれの特性について知りましょう
医学における判断はリスクリターンで判断することが原則です。
依存のリスクがある薬であっても、依存になりにくい範囲内に使用を制限して使用していればリスクとリターンのバランスが取れるので問題がありません。
不安があれば医師や薬剤師にリスクとリターンについて、詳しい説明を求める事が大切です。
ベンゾジアゼピン系
一時期は処方が非常に増えていたこともありましたが、現在は依存性の高さが問題視されて慎重な処方をするようにガイドラインが変更された系統のお薬です。
ベンゾジアゼピン系は睡眠薬の中では、依存を形成しやすく(個人差はありますが2週間以上毎日使用で依存形成が始まると考えられている)、脳の機能低下(ボーっとする、頭が働かない、忘れやすい)やふらつきが強くなりやすいなどのリスクが高い睡眠薬です。
化学構造は抗不安薬と同じもので、抗不安薬によって得られるリラックス効果(+筋弛緩作用)を利用して睡眠を手助けします。
不安を抑制する効果があるので、不安症状がある場合には、そちらの効果も得られます。
単に眠れないというだけで、不安がない場合にはベンゾジアゼピン系を使用する必要性は低くなり、他の薬を選択する余地が出てきます。
ベンゾジアゼピン系の薬を連用すると、海馬、扁桃体、視床の体積が減少(萎縮)することが脳MRIからわかっています。
また、一部の研究では認知症のリスクの増大を疑われていますが、まだ医学的な議論に決着がついておらず、科学的な因果関係は現在のところはっきりとは証明されていません。
非ベンゾジアゼピン系
非ベンゾジアゼピン系で日本で認可されているのは、イミダゾピリジン系(ゾルピデム:マイスリー)とシクロピロロン系(ゾピクロン:アモバン、エスゾピクロン:ルネスタ)という二つの系があります。
ベンゾジアゼピン系と比べると、筋弛緩作用(筋肉を緩ませる作用)が少ない為、ふらつきによる転倒が少ないとされています。
頭が働きにくい、物忘れが起こりやすくなるなどの副作用はベンゾジアゼピン系と似ています。
しかし、ベンゾジアゼピンよりも依存性が低く、8ヶ月程度は依存形成に時間がかかるとの報告もあります。
また、ベンゾジアゼピン系の薬と異なり、長期使用でも脳の一部の体積が減少(萎縮)するといった研究報告も現在のところでていません。
不安症状を和らげるような作用はない為、不安症状が出ていない場合に適していますが、「眠れなかったらどうしよう」などの不安症状が出ている場合には不向きな場合があります。
オレキシン拮抗薬やメラトニン受容体作動薬が効かない場合には、非ベンゾジアゼピン系が選択肢になってきます。
オレキシン拮抗薬
オレキシン拮抗薬は日本が世界で初めて開発した新しいタイプの睡眠薬で以下の3つが現在認可されています。
スボレキサント:ベルソムラ
レンボレキサント:デエビゴ
ダリドレキサント:クービビック
覚醒状態を維持し続けるのに必要なのが、オレキシンという神経伝達物質ですが、オレキシン拮抗薬はオレキシンの作用を邪魔をして、覚醒を邪魔して覚醒を維持できなくするお薬です。
覚醒が維持できないことが結果的に睡眠を促すことになります。(眠りすぎてしまうナルコレプシーはオレキシン不足だと考えられています。)
薬の脳の作用範囲が狭いことから、ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の薬よりも脳への悪影響が少ないと考えられています。
依存性もかなり低く(テキストでは依存性はないとされている)使いやすい薬ですが、人によっては眠れるけれど悪夢を見ると訴えられる場合があるお薬です。
開発されてからの期間がまだ短い為、長期的な脳への影響は詳しくわかっていません。
メラトニン受容体作動薬
夜の眠気を呼び起こすのはメラトニンという神経伝達物質の働きです。メラトニンは体内時計の調整に関わる神経伝達物質です。
メラトニン受容体作動薬はメラトニンと同じ働きをするお薬です。
日本では以下の2種類が承認されています。
ラメルテオン:ロゼレム
メラトニン:メラトベル
眠る時間と起きる時間のリズムがうまく取れない睡眠相リズム障害に特に効果的ですが、他の睡眠薬と合わせて使われることがほとんどです。
生活リズムの乱れから、体内時計が乱れてしまっている方のリズムを再び整える時に用いられるお薬ですが、不眠症から体内時計が乱れないようにといった予防的な理由や他の睡眠薬の補助として使われます。
まとめ
睡眠薬には大きく4種類があり、それぞれ異なる特性とリスクを持っています。
ベンゾジアゼピン系:最も依存性が高く、長期使用で脳の海馬、扁桃体、視床の萎縮のリスクが報告されています。不安症状もある場合にはより効果的です。
非ベンゾジアゼピン系:ベンゾジアゼピン系より依存性が低く、転倒リスクも少ないです。ベンゾジアゼピン系の薬の作用範囲をより狭くしたような薬で、長期使用による脳萎縮の報告はありません。
オレキシン拮抗薬:比較的新しい薬で、依存性が低いとされています。長期的な影響はまだ不明です。
メラトニン受容体作動薬:体内時計の調整に効果があり、依存性が最も低いとされています。
睡眠薬の選択は個人の症状や状態によって決めていくことが大切です。
しばらくの期間、毎日飲み続けるといった使用法の場合にはベンゾジアゼピン系の薬は向きませんし、不安症状もあり、短期間だけでも一度良く眠りたい場合には非ベンゾジアゼピン系のお薬では役不足です。
医師や薬剤師とよく相談し、適切な薬を選択するようにしましょう。
睡眠薬の使用は、そのリスクとリターンを十分に理解した上で、医師の指示に従って適切に行うことが重要です。
鍼灸は副交感神経を刺激する作用がありますが、睡眠薬ほどの強制力がありません。
しかし、最初から自然な睡眠を誘導することができ、薬のような副作用もありません。
当院での改善を希望される方は、不眠症(睡眠障害)をご覧ください。
遠方で当院への来院が難しいけれど、心身の問題について相談したい方はオンラインカウンセリングをご利用ください。