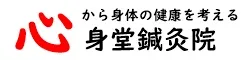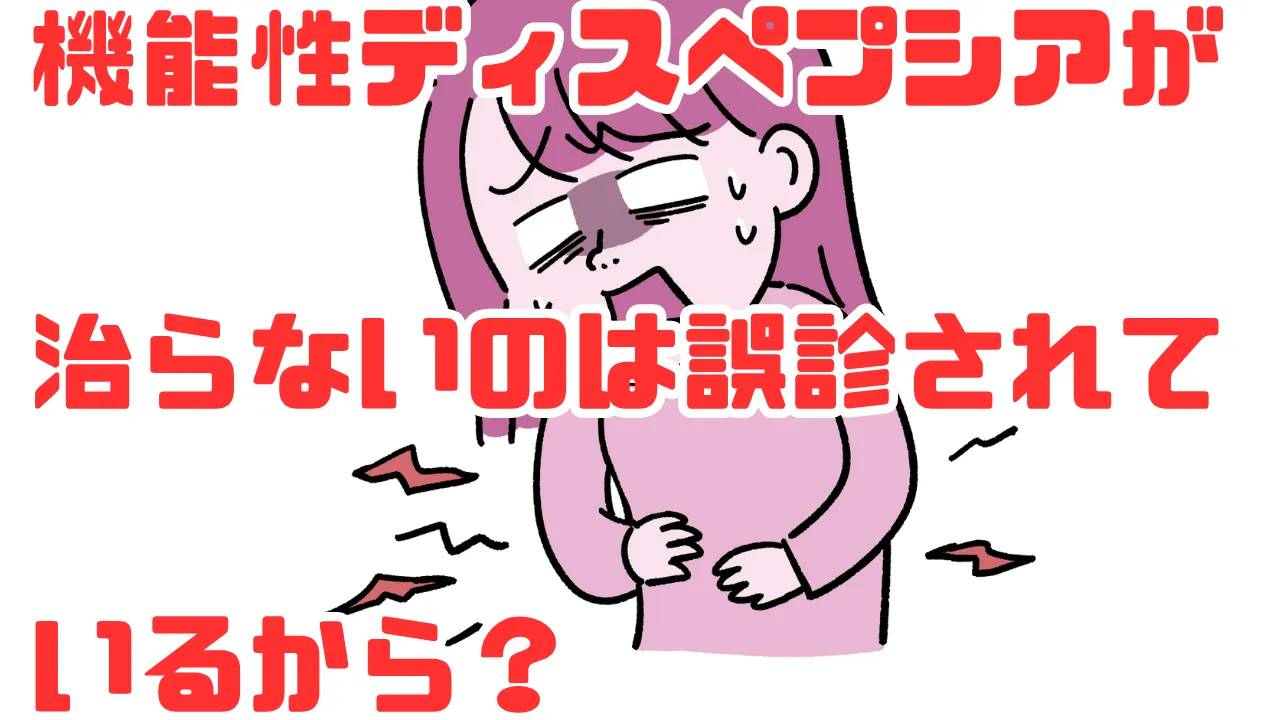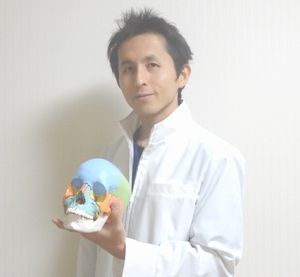
こんにちは、心身堂鍼灸院の佐野です。
食欲がなくなり、ご飯を食べることが出来ない。
しかし、胃カメラ検査でも正常で機能性ディスペプシアと診断されたが、薬を飲んでも改善しない。
症状からは機能性ディスペプシアに該当する症状ですが、誤診になっていることもあります。
今回は機能性ディスペプシアと誤診されやすい精神疾患について一緒に考えていきたいと思います。ぜひ最後までご一読ください。
結論:気分の落ち込みがないうつ病の可能性がある
食欲がなくなって、気持ちが悪いなどの症状があり、消化器内科を受診して胃カメラなどの一通りの検査を行っても原因が見つけられない場合、機能性ディスペプシアと診断されることがあります。
機能性ディスペプシアの診断では以下の4点を基準に診断が行われますが、医師によっては原因の分からない消化器症状全般に機能性ディスペプシアと診断されていることが少なからずあります。
1.診断の少なくとも6か月以上前から症状が始まり、直近の3か月間その症状が続いていること。
2.心窩部(みぞおち周辺)の痛みや灼熱感、食後のもたれ感、早期飽満感のうち1つ以上があること。
3.胃カメラなどの検査で胃や十二指腸に潰瘍、腫瘍、炎症などの異常がないこと。
4.ピロリ菌感染の有無や他の消化器疾患(胆石、膵炎など)を除外出来ていること。
機能性ディスペプシアと診断されているけれど、機能性ディスペプシアの治療を行っても改善が見られない場合は他の精神疾患が隠れている可能性を考えてみる必要があります。
気分の落ち込みがないうつ病の存在
機能性ディスペプシアとの判別が難しい精神疾患として、うつ病があげられます。
「私は気分の落ち込みもないし、うつ病であるわけがない!」と反論したくなると思いますが、もう少し説明をお読みください。
通常のうつ病では気分の落ち込みや悲しみなど何らかの精神的症状を伴うことがほとんどです。
一人で閉じこもって暗い気分で1日中過ごしている。これが多くの人がイメージするうつ病です。
気分の落ち込みがあったとしても胃の調子が悪いから気分が乗らない、やる気が起こらない。という症状が強くあるというだけで、胃の不快症状がなくなれば元通り元気になると感じていらっしゃるのもわかります。
しかし、うつ病の中には気分の落ち込みや悲しみといった精神症状が起こりにくいうつ病も存在します。
診断基準(DSM-5など)では非定型うつ病に分類されるもので、仮面うつ病などと言われたりもします。
仮面うつ病の主症状は身体症状
仮面うつ病の症状は気分の落ち込みや悲しみといった精神症状よりも、頭痛や肩こり、慢性的な疲労感、動悸、胃腸の不調、めまい、倦怠感、腰痛、胸の圧迫感など多様な身体症状が主症状です。
現代の医学では、うつ病も機能性ディスペプシアも検査数値で捉えることが出来ない疾患の為、検査で鑑別することが困難な状況にあります。
手掛かりとして、パニック障害などのうつ病を併発しやすい精神疾患にかかったことがある、血縁の家族に精神疾患の既往がある、機能不全家族で育った、いじめを受けたことがあるなどの既往歴や家族歴、生育環境が参考になります。
また、以下のような性格特性がある場合には、うつ病を疑う余地があります。
・真面目で責任感が強い
・几帳面で完璧主義
・負けず嫌いで執着心が強い
・他人への気遣いが多く、人間関係を円滑に保とうとする
・自分に厳しく、努力家で凝り性
・ネガティブ思考や自己否定が強い傾向がある
・気を遣いやすく、調和を重視する
・感情を抑制する傾向があり、ストレスをため込みやすい
機能性ディスペプシアで診断があっている場合でも、機能性ディスペプシアはストレスによって悪化するという特徴があるため、うつ病と機能性ディスペプシアが併発していることも考えられます。
その場合には、うつ病の治療と機能性ディスペプシアの治療を精神科・心療内科と消化器内科それぞれの専門医の連携のもと、並行して治療を行っていくことが大切です。
精神科・心療内科で抗うつ薬による薬物治療を検討する
胃の不快症状がうつ病が機能性ディスペプシアと誤診されていたり、うつ病が併発している場合であれば、抗うつ薬による薬物治療が有力な治療候補になります。
しかし、抗うつ薬は投与開始時に副作用として、胃腸の不快症状が誘発されやすいという特徴があり、効果を実感できるのは投与開始から2~3週間以降となります。
もともと、胃の不快感が半年以上継続しているところに、更に薬の副作用による胃の不快症状が一時的に追加されることで、忍耐力が持たない方が少なくありません。
体が薬に慣れて副作用が落ち着き、効果が出てくる2~3週間耐えることが出来るか?が問題になります。
うつ病の状態は本人の自覚なしに認知能力の低下が起こっているため、正しくもの事をと判断する能力が低下してしまいます。
その結果、抗うつ薬投与開始直後の副作用だけが目立ち、効果を実感できる2~3週間より前に効果がないと判断して治療をやめる方が多いです。
治らなくても自分にとっては、治療による苦痛が少ない治療法を選びやすくなる傾向があります。
自然療法だけにこだわらない方がベター
症状が身体症状として出てきてしまう仮面うつ病では、鍼灸などの自然療法だけにこだわるのはお勧めできません。
胃腸の不快感に対して、鍼灸施術を行うと一時的に症状は改善されることが多いですが、効果があっても1日程度しか持続しません。
うつ病の二次性の症状として胃腸の不快感が出てきているため、脳からの指令で再び胃腸の不快感が復活してきてしまうからです。
身体症状を伴わないうつ病であれば、心理療法で介入することでストレスを減らして運動療法と休養をすることで改善していくという方法もありますが、身体症状が主体の仮面うつ病の場合はこの方法が使えません。
なぜなら、ほとんどの方は胃腸の不快感がある状態での運動療法が難しく、休養も胃腸の不快感によるストレスの悪影響で仮面うつ病が改善してこないからです。
その為、抗うつ薬で仮面うつ病を改善しながら、鍼灸や運動療法でその効果を手助けするように併用していく方が改善しやすくなります。
まとめ
機能性ディスペプシアと診断された場合で治療がうまくいかない場合は、気分の落ち込みがそれほど発生しない身体症状が主体の非定型うつ病(仮面うつ病)の可能性があります。
機能性ディスペプシアと仮面うつ病は特徴が似ており、鑑別診断が難しい面がありますが、過去の既往や家族歴、生育環境、性格特性などを踏まえてうつ病を疑うことも一つの選択肢になります。
通常のうつ病と異なり、身体症状が主体の為、治療法そのものは休養が重要にはなりますが、身体ストレスのストレスから十分な休養がとりにくいという特性があります。
その為、抗うつ薬を主の治療法として選択することが望ましい病態です。