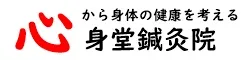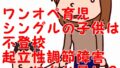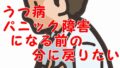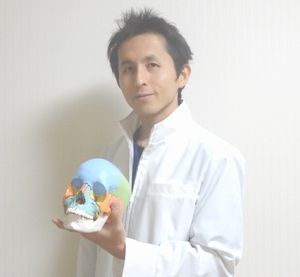
ブログをご覧頂きありがとうございます。浜松市はりを刺さない心身堂鍼灸院の佐野です。
夏休みが明けると学校へ行きたくないという行き渋りがはじまったり、実際に行けなくなってしまう、しばらく学校へ行っていたけれどだんだん休みがちになる子供、朝起きられない、腹痛や頭痛で行けなくなってしまう子供が増えます。
統計的にも夏休み明けは不登校の子供が増加する時期です。突然朝起きられなくなる、不登校になってしまう子供は多いです。
親御さんとしては突然、学校へ行かなくなると焦ってしまいますよね。
今回は夏休み明けに不登校や体調不良になぜなり易いのか?について一緒に考えていきたいと思います。是非、最後までお読みください。
結論:焦っても行けるようにならないので、現状を把握することからはじめましょう
夏休み明けから学校へ行けなくなる、行き渋り、朝起きられない、腹痛、頭痛などの体調不良になる子供は多いです。
夏休み中の生活リズムの乱れ、長時間のデジタル機器の使用などによる身体的な負荷が体調不良を引き起こし体調不良が原因で自律神経系に乱れが生じて、無気力や不安症状がでて「学校へ行きたくない」と口にしている場合もあります。
その場合には、まずは体調を整えることが大切です。
生活リズムを整える(3食食べて、朝起きて夜寝る)、スマホやゲームの使用時間を制限する、毎日適度な運動をして汗を流す、冷たいものを摂りすぎないなど基本的な生活習慣を見直すことから始めていきましょう。
もちろん、学校へ行きたくない気分になるということは心理的な問題が無関係ではありません。
しかし、元気であれば学校から感じているプレッシャーなども跳ね返せるものの、身体的に弱ってしまってそういった心理的な抵抗力が落ちてしまっている場合もあります。
体調が良くなるとどうして学校へ行きたくない気分になっていたのか?自分でもよくわからなくなる場合もありますので、学校へ行きたくないという言葉だけから「心理的な問題」と決めつけてかかる必要はありません。
学校を休ませることそのものは問題ないですが、体調を整える為の休養をしっかりと取ることが大切です。
生活リズムが乱れている、デジタル機器の使用時間が長い場合にはデジタルデトックスに取り組むことから始めていきましょう。
私達の身体は一晩徹夜しただけでもその悪影響が14日間は持続することが研究からもわかっています。(徹夜によりコルチゾールというストレスホルモンの値が上昇し、正常値に戻るのに約2週間時間がかかります。)
夏休み中の生活習慣に問題があった場合には2週間から1ヶ月ぐらいかけて生活リズムを整えた生活を継続して気持ちが上向いてくるのを待ってみましょう。
また、心理的な問題で比較的多いのが受験生の中学・高校3年生の子供たちです。
夏休みぐらいに塾で夏期講習があったり、友人と遊びに行った時に皆勉強の話をしていたり、そういった雰囲気の変化が環境の変化によるストレスとして反応し、自分だけ取り残されている感覚に襲われていたり、志望校に挑戦してもし受からなかったら・・・と不安になっている子供も多いです。
また、3年生に限らず、夏休み明けのテストや課題の提出で、評価されることが怖くなってしまう子供もいます。
このほかにも、夏休み前から心理的にも既に頑張りすぎて不登校になるかならないかの限界ギリギリで何とか夏休み前までは学校へ行けていたが、もう学校へ行くことが出来なくなっていた場合などもあります。
いずれにしても、叱ったり、学校へ行くように圧力をかけても学校へ行けるようになるわけではありませんので、一旦学校へ行くことは諦めて、親が子供の感情に寄り添って学校へ行けないことで責めないという対応がとても大切になります。
腹痛や頭痛、朝起きられないという明らかな症状が出てきている場合には専門家に診てもらうことも大切です。
基本的には生活習慣を整えて体調を戻すことからはじめていきましょう。
生活リズムを整える
夏休み中に遅くまで起きていたり、起きるのが遅かったり、生活リズムが崩れてしまった場合には、体内時計がズレてしまい、身体がいわゆる時差ボケと同じ状態になっています。
体内時計を整える基本は目から光を入れることと、朝食をとることです。
どれだけ体内時計がズレてしまっているのかにもよりますが、私達の身体は朝目から光が入った時間から14~16時間後に眠気がやってくるようにできています。
寝る時間はこの眠気の影響を受けるので、早く寝ようと頑張っても眠れないことがほとんどです。
最初は今起きられる時間に目から光を入れて、朝食をとる(時間帯によっては昼食になるかもしれませんが・・・)ことからはじめていきましょう。
そして、その14~16時間後を目安に眠気を感じたら寝るという生活を行い、少しずつ起きる時間を早めていきます。
運動をして体を疲れさせると眠気が早くやってきやすいので、運動を併用するのもとてもいい方法ですが、熱中症にならないように注意してください。
デジタル機器の依存状態をどう対応するか?
デジタル機器(スマホ、タブレット、ゲーム機、PC、TV)の依存状態は不登校になった後に、家で過ごす時間が長くやることがなくてスマホやゲームで時間つぶしをしているうちに依存症になってしまうことが多いです。
しかし、夏休み中の暇な時間に長時間ダラダラとスマホをいじっていたことが原因で、既にデジタル機器の依存状態になっている場合には予防という段階ではなくなってしまう為、依存症の治療が必要になります。
デジタル機器の依存症はまだ医学的に正式に認められていないものの、脳の活動を調べるとアルコール依存症、ギャンブル依存症と同じ依存状態と同じ脳の活動状態にあることが研究ではわかっています。
依存症の治療の基本は依存対象となるデジタル機器から距離をとることになりますが、単純に取り上げると、親子関係が壊れてしまうことがあるので注意が必要です。
スマホが普及してから約10年
デジタル機器の依存症の治療法はまだ医学的に確立されたものがありませんが、他の依存症と同じように使う時間を減らしていくまたは一定期間使用しなければ改善してくることがわかっています。
現時点においては、子供たちがデジタル機器の依存症に陥り、そこから改善していくにはどのようなアプローチが良いのかを、スマホ依存に陥った子供たちで改善法を模索している段階です。
原理的に良い方法として、デジタルデトックスキャンプが年に数回程度ですが行われており、一定の効果が報告されています。
しかし、気軽にいつでも参加できるというものではないので、今の生活と並行しながらデジタル機器の依存状態をどう改善していくのが良いか?は非常に悩ましい問題です。
デジタル機器に依存しやすい子供は親子のコミュニケーション時間が短かったり、子供の話を十分に聞いてくれる大人がそばにいないなど、子供が不安感を感じやすい環境にいることが多いと言われています。
子供の話をただそのまま聞いてあげるという親子のコミュニケーション時間を多くとるようにすることは有効な方法の一つです。
しかし、親側も仕事に家事に忙しすぎて、物理的にそのような時間をとることが出来ないからこそ、子供がスマホ依存の状態になっていってしまっているのが現実な為、改善が本当に難しい問題です。
心理的問題に対するアプローチ
不登校の改善が難しいといわれる理由はこの心理的な問題が複雑でこれといった解決策が存在しない点にあります。
不登校のステージについては下記記事参照

夏休み明けに学校へ行けなくなっている時に、子供が前駆期にいるのか、進行期にいるのかで大きく状況が異なってきます。
前述したように叱ったり、学校へ行くように圧力をかけないように対応してもらうのは、前駆期にいる子供であれば受容的に対応し、子供が再び自信を取り戻していけば比較的早い段階で学校へ戻ることが可能になるからです。
既に進行期に移行してしまっていた場合でも、親からも叱ったり、学校へ行くように圧力を受けると余計に大きなストレスとなる為、子供の心の逃げ場がなくなってしまいます。
その結果、体調不良が悪化するだけでなく、子供自身も誰も自分の味方はいないと感じて、心を閉ざしてしまいその後の回復期までの期間を無駄に長引かせてしまいます。
進行期に移行してしまっていた場合でも、混乱期、回復期を経れば社会に復帰していくため前駆期、進行期どちらの場合であっても親が味方でいるということが子供に伝わるように接してあげることはとても重要になります。
まとめ
夏休み明けに子供の体調不良や学校への行き渋りが始まると親御さんとしてはとても不安になってしまうのが普通です。
しかし、不登校の問題だけでなく、夏休み期間中の生活リズムの乱れやスマホ依存症から体調不良を起こしている場合もあります。
生活リズムの乱れやスマホ依存症が原因の体調不良であれば、生活習慣を整えスマホの利用時間を制限するなど適切な対応をすることで改善していくことが可能です。
腹痛、頭痛、朝起きられないなどの体調不良が顕著な場合には専門家に診てもらうことも重要です。
心理的な問題を抱える不登校がはじまっている可能性もある為、学校へ行くよう叱ったり、圧力をかけることは避けて受容的な態度で接していくことが大切になります。
当院での改善をご検討の方は不登校、起立性調節障害をご覧ください。
遠方で来院が難しいけれど、カウンセリングを受けたいという方はオンラインカウンセリングをご利用ください。