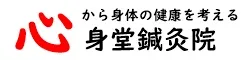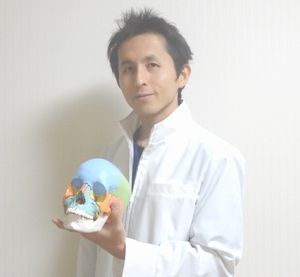
普段何ともない方でも暑いと動悸を感じる事があり、そこから心配や不安になることで交感神経を刺激してしまい更に動悸がひどくなるといった悪循環を繰り返して自律神経失調症や不安障害(パニック障害)へと進行させてしまう場合があります。
今回は暑さで動悸が出る原因と対処法について知ることで、暑さの動悸から自律神経失調症や不安障害(パニック障害)にならない方法について、一緒に考えていきたいと思います。是非、最後までお読みください。
暑いと動悸がする原因と対処法
結論:体温調節と循環血液量の低下で心拍出量や心拍数が増加して動悸を感じやすい
私達の身体は体温をある一定の温度に保つ仕組みがあり、呼吸で体温を外に放出する他の哺乳類とも共通する以外にも、皮膚表面に血液を集中させて体温を放散(放熱)する方法や発汗して汗が気化するときに熱を奪う気化熱による放熱をしています。
体温は医学的には血液の温度とイコールであると考えられている為、体温調節には血液が重要な役割を果たします。
暑くなると血液を皮膚表面に集めて効率的に放熱して体温調節を行おうとします。
放熱の為により多くの血液がとられるため、他の臓器が使用する血液の不足分を補うために、体は心拍出量と心拍数を上げて血液循環の速度を速めて対応します。
放熱のために上げた心拍出量と心拍数が動悸として感じられてしまうことが多く、人によっては動悸から不安になってしまいその心理ストレスで自律神経失調症やパニック障害へと進行してしまう場合があります。
暑い時に身体に何が起こっているのかを理解することで、不要な心理ストレスを抱え込んで自律神経失調症やパニック障害を引き起こさないように予防していくことが大切です。

体温を下げる為には血液を体表面に集める必要がある
体温を下げる一番シンプルな方法が体温の放射です。
スマホを使いすぎると表面が熱くなるのと同じで、身体の外に熱を逃がすために身体の表面に熱を集中させた方が効率的に熱の放熱が出来ます。
その為に胃腸などの内臓や脳へ送られる血液量を減らして、放熱の為に皮膚表面へ血液を集中させます。
暑くなるとだるくなったり、食欲がなくなる、意欲がなくなるなどは、体表面へ血液が送られるため、胃腸や筋肉、脳への血流が制限されるために起こります。
血管が拡張すると循環に必要な血液量が増加する
血管は筋肉で出来た管です。
体温はほとんど血液が保持している熱なので、身体の外に熱を逃がすために身体の表面に熱を集める為には皮膚表面の血管を拡げてたくさんの血液が皮膚表面に集まるような状態にする必要があります。
血管が拡張することで皮膚表面により多くの血液を集めることが出来るのですが、血管が拡がることは血管内の容積が増大することとイコールです。
血管の容積が拡がると身体全体で血圧を維持する為に必要な血液量が増加します。
血液量の不足を補うために、身体は心拍出量と心拍数を増やして血液の循環を速めることで血液量の不足分を補おうとします。
発汗で血液量が減少する
更に効率的に体温を下げる為に、人間には発汗というシステムがあり、全身から汗を出し、気化熱によって体温を下げようとします。
発汗により体温は下がりますが、汗の原料は血液中の水分です。
血液は血漿(55%)と血球(45%)が混じった液体ですが、血漿の約91%は水です。つまり、血液の約50%は水ということになります。
発汗によって血液中の水分が失われると血液量が減少します。
発汗した分と同量以上の水分とミネラル(塩)が補充されていないと、血液量がどんどん不足していくことになり、その不足分も心臓が頑張って血液を回す必要が出てきてしまうのです。
血管拡張と発汗で不足した血液量分を心拍出量と心拍数を上げて対処する
血液量が減ると血圧を維持していくために、心臓から送り出す血液量を増やす必要に迫られます。
心臓そのものの収縮・拡張をより大きくして1回の心臓の拍動で送り出せる血液量を増やす(心拍出量)だけでなく、心拍数を上げてより多くの血液を全身に送り出すことで、不足した血液量分の血液を全身に届けようとします。
運動している時と似たような状態になります。
しかし、運動しているわけではないので、心臓の拍動が大きくなり、心拍数が増えるので心臓の拍動を自覚しやすくなります。
これを動悸として感じることになるのです。
暑さによる動悸の予防法
暑さによる動悸は不快なものですが、まずは熱中症になりかけていないか?といった観点を優先的に確認する必要があります。
予防は熱中症と基本的には同じで血液量を保持するために、塩と水分補給を十分に行う。
体温が上がりすぎて体温を下げようとしている状態ですので、涼しい場所へ移動して体温を下げるなどが基本となります。
お勧めの体温の下げ方
体温が高くなっている場合には先にある程度体温を下げてしまうほうが効果的です。冷房の部屋にいるのも悪くはありませんが、水シャワーを浴びると効率的に体温を下げることができます。
水は空気よりも熱伝導率が高いため、約25倍速く体温を奪います。
原理的に言えば20度の部屋に25分いるのと20度の水を1分浴びた場合は熱伝導率で言えば同じ効果を得ることが出来ます。
また、水シャワーを浴びると皮膚表面血管が一度、冷刺激により収縮します。皮膚表面の血管が収縮することで、体温の放熱の為に制限されていた脳や内臓への血液量が増加する為、他の臓器の機能が回復します。
長時間水を浴びていると今度は冷えすぎてしまいますので、冷やしすぎないように注意しながら、行ってください。
冷たいものを食べて体温を下げない
冷たい飲み物、アイス、かき氷など、冷たい食べ物で体温を下げようとするのはなるべく控えましょう。
血管は冷やされると収縮するようにできていますが、胃腸は特に冷えに弱い臓器です。
元々体温を下げるために胃腸への血流が低下した状態のところへ、冷たいものの飲食によって胃腸の血管をさらに収縮してしまうと胃腸の機能低下を引き起こしてしまいます。
胃は冷たいものを食べるように元々できていない為、冷やされることに対して脆弱です。
どうしても冷たいものが食べたい場合は、口の中で冷たさがなくなるまでとどめてから飲み込む、暖かい飲み物と一緒にとるようにするなど、胃を冷やさないように注意しましょう。
日頃から運動して心肺機能と体温調節機能を高める
動悸の予防に一番効果的なのは、普段から有酸素運動をして心拍数を上げて下げる。運動により体温を上げて下げる身体の体温調節機能を十分に使用しておくことです。
人間の身体の機能は使うことで維持され、使わないことで失われていきます。(医学の世界にはUse it ,or lose it.(使うか失うか)という言葉があります。)
運動によって心肺機能を高い状態にし、体温調整機能も普段から使っていると、肉体的には動悸は起こしにくくなります。(水分補給は必要です。)
今まで、運動していなかった方が暑さで動悸が出始めた予防として、真夏から運動を始めてしまうと熱中症のリスクの方が高くなってしまうので、1年ぐらいかけて身体の機能を取り戻すつもりで涼しくなる秋ぐらいから運動を始めてみることをお勧めします。
暑さから動悸を感じるメカニズムを理解して、必要以上に不安にならない
動悸は命に直結する心臓に関わる問題なので、不安になる方は多いです。
一度、循環器内科を受診して一通りの検査を受けた上であれば大丈夫なので、動悸を感じた場合にはまずは一通りの検査を受けて頂いて、問題がないことを確認することから始めましょう。
自律神経の乱れが根本にある場合は自律神経に対するアプローチが必要になりますが、暑いと動悸が起こるのは生理学的にも正常な反応なので必要以上に不安になる必要はありません。
暑さから動悸が起こるメカニズムを理解し、水分補給、体温を下げる、心臓と肺を鍛えるといったことを実践していきましょう。
まとめ
暑さによって動悸を感じやすくなる理由は、体温を下げる為に血液量が低下してしまい心拍数や心拍出量を多くすることで暑い環境に適応するための正常な反応です。
熱中症に近い状態でもあるので、水分補給をしっかりと行うことと、適切な方法で体温を下げることが重要です。
また、日頃から有酸素運動を行うことで体温調節機能や心臓や肺の機能を高めておくと、心拍数や心拍出量を多くせずともある程度の気温までは適応できるように鍛えることも可能なので、運動習慣がない方は暑さが弱くなる秋ごろから運動を開始しましょう。
動悸を感じると不安になるのは普通なので、まずは心臓に異常がないかを循環器内科で一度検査してもらいましょう。
そのうえで問題がなければ水分補給、体温を下げる、運動などを生活に取り入れていくと良いです。
自律神経の乱れから動悸が出ている場合には、適切なアプローチが必要になりますので、水分補給と体温を下げることを行っても動悸が治まらない場合には専門家に相談しましょう。
当院での改善をご検討の方は自律神経失調症をご覧ください。
遠方で来院が難しいけれど、カウンセリングを受けたいという方はオンラインカウンセリングをご利用ください。